


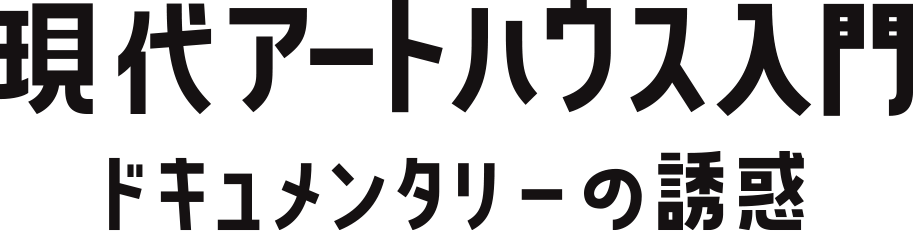

1970年代から今日まで続く日本の〈アートハウス〉は、ミニシアターという呼称で親しまれてきました。そこは世界中の映画と刺激をもとめる観客とが出会う場所であり、多様な映画体験によって、未来の映画作家だけでなく、さまざまなアーティストを育む文化的ビオトープとしての役割を担ってきました。〈アートハウス〉の暗闇でスクリーンが反射する光を浴びることは、多かれ少なかれ―私たちの生き方を変えてしまう体験なのです。
「現代アートハウス入門」は、〈アートハウス〉に新しい観客を呼び込むため、コロナ禍真っ只中の2021年にはじまった施策です。その第三弾となる巡回上映「現代アートハウス入門 ドキュメンタリーの誘惑」では“ドキュメンタリーと呼ばれる方法で作られた映画”にフォーカスします。
まず、18名の気鋭の映画作家に次のようなアンケートに協力していただきました。
アンケートの回答を公式WEBサイトで発表し、さらに名前のあがった作品群から選りすぐりの7本によるプログラムを組み、東京・ユーロスペースをはじめとした全国の〈アートハウス〉で巡回上映を実施します。
古典的名作からコンテンポラリーな傑作まで。ぜひこの機会に“ドキュメンタリー”の多様な方法と視点の面白さをご堪能ください。

10代の頃、たまたまNBA選手を目指す少年二人のドキュメンタリー『フープ・ドリームス』を観た。ドキュメンタリーの面白さと底の深さに初めて心を揺さぶられた。職業俳優に脚本上の人物を演じてもらうのではなく、社会に生きる本物の人間を、長い年月をかけて追いつづける。そのことのもつ重みに衝撃を受けた。夢を追う少年たちの姿と、彼らを待ち受ける冷徹な運命には、いつの時代でも人の心を打つものがあるはず。
映画の道を志してから数年後。幸いにも敬愛する深作欣二監督に会う機会があった。大学生だったわたしは深作監督を学校にお呼びし、映画の授業をしてもらった。事前に深作監督から、「お前、俺を呼ぶなら俺の作品を全部見とけよ」と言われた。深作監督は貧乏学生のために全作品をVHSで送ってくれた。その中の一本に、「映画は戦場だ 深作欣二in『バトル・ロワイアル』」というドキュメンタリーが混ざっていた。見て震えた。戦後の日本で無数の映画を作ってきた70才近くの老人が、まだ若き10代の少年少女の俳優たちへ向かって、声を枯らし(クランクイン前にすでに喉が枯れている!)全身全霊で演出に当たっている。映画とはこれほどまでのエネルギーで作られるものか。今でも油断しそうになったら、このドキュメンタリーを思い返している。
“記録”というドキュメンタリーの一側面を見れば、『東京裁判』は必見で、これを記録していた当時の人たちはすごい、としかいいようがない。二度と戻らないことを記録しておく、ということ。それ自体が価値を持つという証のような映画。現代のように不都合な記録はどんどん破棄していく時代にあっては、特に。
一方で『ゆきゆきて、神軍』は、撮影者と被写体の共犯関係でとてつもない領域まで踏みこんでいく。ドキュメンタリーがただの“事実の記録”とは違う、ということをこの映画は強烈なまでに叩き込んでくれる。何度も再見しているが、何度目かに観直した時に気づいたことがあった。本作の主人公である奥崎謙三氏が、かつての上官の家に処刑事件の追及のため乗り込んでくる。その町が、わたしの地元だったのだ。どうやらわたしが幼少期に遊んでいた町で、奥崎氏は激昂していたのだ。映画がわたしの人生と不意にリンクした瞬間、ドキュメンタリーだからこそ思わず震撼した。『コレクティブ 国家の嘘』は2019年製作の映画で、最近もっとも衝撃を受けたドキュメンタリー。恐るべき国家的な隠蔽事件を暴いていくが、あまりにも次々とドラマティックな展開が訪れるため、思わず「おもしろい……」と呟きたくなる。その瞬間、果たしてその感想は正しいのか? お前の生きてる社会はどうなんだ? と刃が自分に向いてくる。これもまたドキュメンタリー映画ならではのことかもしれない。
1979年生まれ。09年、『SR サイタマノラッパー』で映画監督協会新人賞など多数受賞。11年『劇場版 神聖かまってちゃん ロックンロールは鳴り止まないっ』で高崎映画祭新進監督賞受賞。主な劇場公開作に『22年目の告白』(17)、『シュシュシュの娘』(21)、『聖地X』(21)など。ドラマ演出に「ネメシス」(21)など多数。

圧倒的な年月をかけて子どもと大人の関わりを描いたのが、『隣る人』(2011年/刀川和也)だ。児童養護施設に8年間密着し、少しずつ大きくなる子どもや、その過程に関わる大人の姿を映し出す。子どもに関する作品は多々観てきたが、これほど密にそこにある日常を捉えたものは他になかった。ナレーションもテロップもない潔い編集で、決して「かわいそう」という無責任な視点に立たず、彼ら・彼女らをじっと見つめ続ける。どんなときも「隣る人」であり続けようとする子どもと大人のように、カメラもそっと隣り合ってそこに存在している。
独特なスタイルで「家族」を定義しなおしたのが、『沈没家族 劇場版』(2018年/加納土)だ。1995年、東京の片隅で「沈没家族」と名付けられた共同保育があった。そこで知らない大人に囲まれて育った“土くん”が、大人になってカメラを持ち自らのルーツをたどる。ヒッピーのような保育人たち、常識にとらわれない母、そして不在だった父。一風変わった共同生活を紐解くなかで、新しい家族の形が見えてくる。同じ東京、同じ時代にこんな育ち方があったのかと、私は驚きと少しの憧れを抱きながら“土くん”をめぐる旅を見た。
ところ変わって、大阪市西成区釜ヶ崎の「こどもの里」を追ったのは『さとにきたらええやん』(2015年/重江良樹)だ。“日雇い労働者の街”と呼ばれるこの地域で、拠り所となっている“さと”。下町の人情やユーモアと、その裏に潜むそれぞれのしんどさが、ないまぜになって独特な空気を放つ。「悪いけどあたしはあんたの味方だから」という優しい叱り文句、子どもたちが思いっきり駆けることのできる道、路上のおじちゃんに手渡す温かいスープ。大人も子どもも様々な事情を抱えながら、街ごと支え合って生きていく。
数ある東海テレビのドキュメンタリーの中でも、毎年観たいと思える傑作が『人生フルーツ』(2016年/伏原健之)だ。「人生は、だんだん美しくなる。」というコピーの通り、90歳と87歳の夫婦の暮らしぶりが本当に美しい。豊かな庭で季節を感じ、風通しの良い家で大切な人を想う。私はこの作品をきっかけに、「時をためる」ということを意識するようになった。こつこつ、こつこつ……。お金にも名誉にも代えられない生き方がある。自分の軸がぶれそうになるたびに、この作品を見返す。
何度見ても新鮮な衝撃を受けるのが、『ゆきゆきて、神軍』(1987年/原一男)である。学生のころ、何の気なしにミニシアターで観て度肝を抜かれた。何を言っているのかよくわからない部分も多々あるが、主人公・奥崎謙三の覇気がすごすぎて見続けてしまう。信念が人をここまでにするということ、正義が狂気になりゆくこと、戦争の愚かさ……。初めはただの「ヤバいやつ」だったものが、みるみる奥行きを持って迫り来る。
白黒つけることも、右と左で分けることもできぬ世界の混沌そのものに、寄り添い、面白がり、時に腹を立て、時に慈しむような、人間らしいドキュメンタリーが好きだ。どうしようもない世界と、どうにかしたいと人々との間で、スクリーンは私たちを試すように光る。他者がいて、私がいて、世界があるということを、その間たしかに感じられる。だから私は、映画館へドキュメンタリーを観に行く。
1996年生まれ。『イノセント15』(16/甲斐博和監督)で映画初出演。2019年にはNHK連続テレビ小説「まんぷく」に主人公夫妻の長女・立花幸役として出演。そのほか主演作に、映画『ビューティフルドリーマー』(20/本広克行監督)など。21年には監督・脚本・編集を務めた初長編映画『海辺の金魚』が公開されるなど、映像作家としても活躍。

『マルメロの陽光』は私にとって宝石のような作品です。この映画の優しい光、目の前のものを(光で、絵の具で)描くという営みを思い出すたびに心が安らかになると同時に、人間や自然を探求する映画言語(表現方法)の可能性に奮い立ちます。カメラの前に在る(あらゆる存在を含む)他者との距離感が好きです。カメラ前後の境界が融解するような心地がこの映画にはありますが、他者が他者として存在する敬意も感じられます。この距離感、じぶんとは違う他人をうつしとらえる適切な位置というのは、撮影者個人、制作チームの総体的個性やその目的意識によって、違ったものになるのではと思います。じぶんが影響を受けただろうと思う他作品のことを思い浮かべながら考えてみます。作り手にとって(そして観る人にとって)作品を共につくることになる他者(性)とはどんなものでしょうか。それがない作品というのは、私の知っている世界(余白なし)/私の一方的メッセージ/私に理解されたあなた、という枠内に、カメラの前の未知を縛るのではないかとじぶんは考えます。
『あの家は黒い』は詩人でもあったファッロフザードさんがハンセン病の療養所を撮った短編です。ハンセン病患者支援会に依頼され製作されました。ファッロフザードさんは療養所の日常をうつし、ハンセン病患者を可視化しました。顔、患部、歩く姿、食事、リハビリ、教室の風景を、コーランからの引用文やファッロフザードさんの詩を読む声と共に、観客は見聞きすることになります。この作品における他者(性)とはなんでしょうか。作り手にとって、それは被写体となる目の前の療養所の人々と、彼らに向けられる(己も持っているかもしれない)社会的な差別や偏見の意識、ではないかとじぶんは思います。このふたつに揺さぶられながら、他者への想像力に繋がる映画をつくられたのではないかと。大島渚さんの『忘れられた皇軍』も短編です。テレビドキュメンタリーとして制作、放映されました。第二次世界大戦で日本軍として戦い、負傷したのにも関わらず、戦後十分な補償を得ることのできなかった「元日本軍在日韓国人傷痍軍人会」の人たちを撮した作品です。私はこの作品をはじめてみたとき、作り手のその怒りに居心地の悪さを感じました。それは、日常でひとがなにかに怒っている場面に出くわしたときなどに、穏やかに過ごしたいのに嫌だなぁと思う気持ちと似ていますが、それ以上に、なんだかじぶんが責められているような気がしたのを思い出します。大島さんが実際にどの程度まわしていたかは存じませんが、人と人との距離感をはかりつつではなく、「(観客は)見ろ!」「(私は)見てるぞ!」というカメラで、傷痍軍人の人たちを切り取っています。また話は戻りますが、大島さんにとって、この作品における他者(性)とはなんだったでしょうか。カメラの前にいる元日本軍在日韓国人傷痍軍人の方々、彼らのことに関して無関心な日本人と無責任な国。なんだかじぶんが責められている気がした、と先ほど書きましたが、実際に、それは私の問題だという潜在意識がどこかにあるからこそ、居心地が悪かったのだと思います。私についての映画だ、ここには私がいる、と感じる映画との出会いはいくつかありますが、『忘れられた皇軍』のような表現でぶつかってくる映画に出会ったことはなかったです。ぶつかってくるような距離感であることが、この映画における「じぶんとは違う他人をうつしとらえる適切な位置」なのかもしれません。怒りの中にの、引き裂かれるような痛みや悲しさの感情を感じます。作り手にとって他者(性)は、自己と複雑に絡み合っているものなのかもしれないと思います。
最近、知人や友人と「他者(性)」について、「想像力」についての話をしていたので、今回はそれにからめておすすめ作品のいくつかについて書きました。『おてんとうさまがほしい』は、私がサラエボの映画学校から帰国し、佐藤真さんという作家を知った際に、編集者の秦岳志さんからおすすめされて見た作品です。明確な脚本や構成がなくとも、撮影された素材は、編集によって映画になることを学びました。佐藤真さんによる編集も素晴らしいですが、その撮影の実直さからくるイメージの美しさに胸を打たれます。『Palms(Ladoni)』は在学中にカルロス・レイガダスというメキシコの映画作家が観せてくれた映画です。この映画のことをじぶんはとても大事に思っているのですが、まだ言語化したくない、できない気がするので、タイトルの言及のみにさせていただきます。『マルメロの陽光』はポルトガルの同級生が、『あの家は黒い』はJ・ローゼンバウムさんが観せてくれました。
上記じぶんの紹介文で役に立つかはわかりませんが、気になるものがあれば嬉しく思います。
1987年生まれ。フィルムメーカー。アーティスト。2015年の長編第一作『鉱 ARAGANE』が山形国際ドキュメンタリー映画祭2015・アジア千波万波部門で特別賞を受賞。2019年に発表した『セノーテ』はロッテルダムや山形といった国際映画祭で上映され、第1回「大島渚賞」を受賞。2021年、『セノーテ』の成果により第71回芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞。

自宅の近くに、もうだれも住んでいないであろう小さな平屋があった。こじんまりとしたその家屋は、おそらく主がいなくなってからまだそう長い時間は経っておらず、かすかにまだ生活のかおりの名残のようなものがあった。家があった頃は特に大きく気に留めることもなかったのだが、数カ月前、家は取り壊され跡形もなくなった。ぽっかり空いた更地にはやがて雑草が生え始め、気が付くと立派なチョウセンアサガオが花を咲かせていた。きっとこれからチョウセンアサガオをどこかで見るとき、あの平屋のことをときどき思い出すだろう。顔も名前も知らないかつての生活者に対して緩やかに思いを馳せ続けていきたい。
今回挙げた五本のドキュメンタリー作品は私にとって、日々の生活のなかで「緩やかに思いを馳せ続けている」作品であり、自分自身が作品制作をするとき、拠り所にしている映画群でもあります。
どの作品にも〈まなざし〉が存在しています。私はよく、作品の説明をするときなどにこの〈まなざし〉という言葉を遣うけれども、未だうまく説明できたことがありません。ひとつ確信していることは、作り手と対象との距離が近すぎても遠すぎてもまなざしは生まれず、たとえカメラの、フレームの中に捉えられなかったとしてもまなざしは存在することが可能だということです。ここで言う「距離」は物理的なものだけでなく、精神的な・関係性の距離も含みます。寄り添いながらも傾きすぎないニュートラルな視点と、名付けようのない曖昧な関係がまなざしを生むひとつの鍵になっている気がします。そういえば、五作品のほとんどが、題材となっているその土地・場所とは本来ゆかりのないいわゆる「余所者」による作品だったり、もう実際会って話すことのできない、亡き人を語るべき対象としていたりします。
ある事象が正しいか正しくないか・事実か事実でないか、もちろんそれは大切なことかもしれないけれど、その二つの点の間で揺らいでいる・こぼれ落ちてしまいそうな物事や、つかみどころのない曖昧な真実に目を向け耳を傾けていきたい。これらの作品を観るたび、いち作り手としてそう強く思います。私(たち)が生きているこの世界と地続きにある場所で、映画の中の人々は確実に生きていたし今も生き続けている。作品を観返せば感触が何度でも蘇り、この世界に絶望をしないために物を作り続けることの背中を押してくれます。一本一本比べてみると共通項もあれば全く違う部分ももちろんありますが、こんなところが、私が挙げた五本の作品に通じているところなのかな、と思います。
1985年生まれ。2014年、長編初監督作『螺旋銀河』を発表。同作は第11回SKIPシティ国際Dシネマ映画祭でSKIPシティアワードと監督賞をW受賞、ニッポン・コネクションでニッポン・ビジョン審査員賞を受賞。2018年の『王国(あるいはその家について)』は英国映画協会が選ぶ「1925~2019年、それぞれの年の優れた日本映画」に選出された。

前々回の「現代アートハウス入門」で上映されているのですが…外せなかった一作、「暮らしながら撮る」つくり方があることを最初に教えてくれた映画です。7人の若いスタッフたちが阿賀野川流域に移り住んでつくられました。新潟水俣病の被害も、人のこころも、簡単にはカメラに映らない。一緒に暮らせば映せるものでもない。じゃあ何を撮ればいいのか、どうしたら映画になるのか。葛藤の3年間、映らないものに向き合い続けたからこそ、いま見えている世界、患者であることもひっくるめて、川と生きたひとの人生という真実を、そのままに映し出すことのできた作品なのだと思います。
明治生まれの染谷カツさんは、成田空港の二期工事が差し迫る三里塚・東峰の地で、一人、畑仕事を続けています。そこにやってきたのが、小川プロから離れ、一人、三里塚に戻った福田克彦監督でした。一対一の関係性の中で撮る、また監督が撮影、編集まで「一人でつくる」ことは、いま誰でもできてしまう。私もその一人です。それが最善なのか答えが出ませんが、この作品を見ていると、一人のひとに出会ってしまったことで始まる、ドキュメンタリーならではの物語、表現できる世界ってあるのだなと思います。同時録音の画と音を切り離し、カツさんの「動き」と「語り」それぞれの時間軸で重ね合わせる発見をした、編集・構成もとても好きです。
福祉施設内の日々を記録し、撮られた人もみんなでラッシュを見て話し合う。気づいたことが現場に活かされ、その変化をまたカメラが記録する。柳澤壽男監督は、このドキュメンタリーのつくり方を「行って来いの関係」と名付けました。福祉映画5部作のうちの3作目、まさにこのタイトル通りの映画です。愛知県知多市、共同作業所「ポパイの家」を立ち上げていく過程を追っていきますが、メンバーさんたちの意見を聞きながら設計図ができていく場面など、現場の進み方と映画のつくり方がシンクロしています。カメラのあちら側とこちら側の境界線を揺るがしていくことは、社会の側に、あるいは私たちの内面にある差別の壁を取っ払う力になっていく。『阿賀に生きる』でカメラマンを務めた小林茂監督がスチールで参加した、最初の柳澤作品でもあります。
『極北のナヌーク』など現地住民との協働作業によってドキュメンタリー映画を築いたことで知られるロバート・フラハティ監督のフィクション映画です。石油会社の依頼によって作ることになったこの作品も、1年2ヶ月ルイジアナの川辺に家を借りて制作にあたっています。油田掘削を進める作業員と自然の中で暮らす現地住民の少年が出会う物語ですが、両者を「開発者」と「現地住民」という対立した関係性の中で描くことをしていません。大きく雄大な川という映画の舞台に、どちらの世界にもそれぞれの生と死のリアリティがあることを写し込んでいきます。フラハティの「カメラに写るものすべてを拒まずに見つめ続ける」という態度を、私は貫ける自信がありません。ただ等しく見る、写せる地点を見つける作品を、ドキュメンタリー、フィクション関係なくいま作れるのだろうかと考えさせられます。
こちらもフィクション映画なのですが、ドキュメンタリー映画をつくり始める人の物語です。キェシロフスキは、初期にドキュメンタリー映画を手掛けていた監督でもあります。主人公はカメラを手にしたことで、撮ること、作品をつくることへと、のめり込んでいきます。またカメラは他者を次から次に巻き込んでいく道具にもなり、出会いも訪れますが、とにかくあらゆる失敗に転じていきます。この失敗たちは、撮りたい欲望を持った人なら、どれも痛いくらいわかると思います。だんだん笑って見ていられなくなる気持ちになるのがまたいい映画だと思いました。ドキュメンタリー映画をつくることを自ら絶ったキェシロフスキ、その狭間の時期につくられていて、おそらくドキュメンタリーとして撮られた素材も混ざっています。プロとアマチュア、ドキュメンタリーとフィクション、その間にある、つくり手のこころの揺らぎがそのままに焼き付いていて、胸をうつ作品です。
1989年生まれ。代表作に『息の跡』(2016年)、『空に聞く』(2018年)。アートユニット「小森はるか+瀬尾夏美」として2014年に『波のした、土のうえ』を制作、同じく2019年に発表した『二重のまち/交代地のうたを編む』は、シェフィールド国際ドキュメンタリー映画祭コンペティション部門特別賞、令和3年度文化庁映画賞文化記録映画優秀賞を受賞。

まず、私が大好きな映画、次に『ダゲール街の人々』を除いて、若者が多く出演する作品を選びました。それは新しい人たちにとって映画をより身近に感じてもらえるのでは、と考えたからです。最後に、私が映画を作る際、その作法や佇まいが常に私を勇気づけてくれた作品でもあります。
フィリベールは、私が最も敬愛する映画監督の1人です。『ぼくの好きな先生』を初めて観たのは、まだ私が20代半ばの頃でした。スクリーンに映る子どもたちの生き生きとした表情や人間関係がとても魅力的で、圧倒されたのを覚えています。いつの日かこのような映画を自分も作りたい、そう思わせてくれた映画でした。
ヴァルダもまた、私が尊敬してやまない映画監督であり、映画とは「撮るように生き、生きるように撮る」ものだと教えてくれた人でもあります。彼女の映画は身近な題材をエッセイのように綴っていくスタイルであり、『ダゲール街の人々』も例外ではありません。この作品は、彼女が子育てをしている最中に自身が住むパリのダゲール通りを映し出したものです。彼女がこよなく愛した下町で暮らす人々の姿は、「人生とは何か」をそっと教えてくれました。愛する人々に対する恋文のような映画を作り続けたヴァルダは、そもそも「映画」への恋文を綴り続けたのだと思います。
他の3名の監督たちは、私と同世代の映画監督たちです。彼らの作品はとても刺激的で、映画を観る歓びと驚きを教えてくれます。『宝島』は、一見何の変哲も無い避暑地のひと夏のスケッチです。ところが見続けると、忘れかけた幼き日の記憶や登場人物が繰り広げる小さな冒険にどっぷりと浸っている、そんな映画です。『トランスニストラ』もまた、ひと夏の若者の物語ですが、この映画はある緊張感を持っています。それはこの映画の舞台となったトランスニストリアが、ウクライナとモルドバの境界にあり、1990年に独立を宣言した小国であるということが影響しているのですが、それを差し引いてもこの映画はとてもスリリングです。ある少女と5人の青年たちをめぐる恋と友情の駆け引き、やがて訪れる将来への不安、そして思春期特有の無為な時間が繰り返されます。この何でもない青春の一瞬が、永遠に続いて欲しいと願わずにはいられません。『トトとふたりの姉』は、社会の閉塞感がより際立ち、子どもたちへの感情移入を禁じ得ません。彼らの人生への困難を思うと胸が苦しくなります。ただ、そんな暮らしの中にも歓びや安らぎがあることが垣間見え、子どもたちの生きる強さを信じさせてくれる映画です。
5本の映画の作り手たちに共通しているのは、彼らが「世界」に向ける眼差しの確かさだと思います。この世界を丸ごと肯定しようと試みるのと同時に、社会に対してとても冷徹で厳しいものを持っています。
これらの映画を観終える時、私は今もどこかで生きている彼らの人生にふと思いを馳せます。そんな体験も、ドキュメンタリー映画の醍醐味の1つかもしれません。
1981年生まれ。2012年の監督デビュー作『ドコニモイケナイ』で日本映画監督協会新人賞を受賞。2019年の『春を告げる町』は山形国際ドキュメンタリー映画祭、DMZ国際ドキュメンタリー映画祭で上映される。日本映画大学の講師として後進の育成に尽力し、田中圭監督『桜の樹の下』、國友勇吾監督『帆花』などのプロデュースも手がける。

映画はロマンであると常々思っています。ロマンを追い求める映画が好きですし、私はいつもロマンを追い求めて映画を作っていますし、映画の真の力はロマンにあると思っています。なので、私が選んだ5本はロマンを基準にしました。また、ドキュメンタリーという括りではありましたが、うち4本はフェイクドキュメンタリーを選びました。
『光と闇の伝説 コリン・マッケンジー』は架空の伝説的フィルムメイカーを追ったフェイクドキュメンタリーで、リアルな地点から始まり大ボラを吹きまくる終盤に笑いつつも、その根底は映画のロマンを求める作り手へのリスペクトに満ちており、表現に込められた監督のロマンに対する拘りという点においては、紛れもなく真実でありドキュメンタリーであると感じます。
『スパイナル・タップ』は架空のヘヴィメタルバンドを追ったフェイクドキュメンタリーです。派手でかっこいいステージの裏側では人間臭くてバカバカしい出来事や揉め事が繰り広げられ、その様は映画の制作現場の裏側がガムテープまみれである現実とも重なり、ロマンを求める滑稽さと感動とを柔らかに知的に描出した映画であると思います。
『ノロイ』は私の監督したホラーで、公開当時「ほとんどが実際の映像で、一部は再現したもの」という説明で宣伝されたフィクションなので、かなりの出来事は起こるもののもしかしたらどこかで起こったかもしれない範囲でドキュメンタリー風に作られています。いわばヤラセであり、モンド映画であると言えます。これは劇中の作り手が恐怖の根源というロマンを追い求めて破滅していく物語であり、私自身としては誰にも明かさないまま心霊ホラーのフリをしてコズミック・ホラーを描くというロマンを込めた映画です。
『オカルト』も私の監督作でフェイクドキュメンタリーですが、『ノロイ』と違って最後まで見れば誰もがフィクションとわかる内容です。しかし当時のネットカフェ難民の要素を取り入れたり、移ろいゆく新宿や渋谷や吉祥寺の風景を切り取り、『ノロイ』以上に実際のドキュメンタリーに近い部分がありつつ、異世界へ旅立つフィクション性の高いラストを迎えます。これはまさに現実では成し得ないロマンを、ドキュメンタリーの手法が持つリアリティの力で補強した映画です。
『ハート・オブ・ダークネス』のみ、フランシス・フォード・コッポラ監督の妻が『地獄の黙示録』の舞台裏を追った本物のドキュメンタリーですが、芸術的超大作映画の果てしない現場地獄で、トラブルに見舞われまくって全てを失う可能性すらある中、映画作りに執着し続ける監督のロマンへのあくなき挑戦に戦慄と苦笑を繰り返しながら感動してしまいます。
これら5本を見ていただけると、映画作りとロマンとの関係性を強く感じられるのではないかと思い、選出しました。
1973年生まれ。2004年『呪霊 THE MOVIE 黒呪霊』で商業映画監督デビュー。主な劇場公開作に『ノロイ』(05)、『オカルト』(08)、『貞子vs伽椰子』(16)、『不能犯』(18)、『恋するけだもの』(20)、配信ドラマに「未来世紀SHIBUYA」(21)など。8月27日より劇場版『オカルトの森 THE MOIVIE』、9月30日より『愛してる!』が劇場公開。

学生時代に水道橋のアテネフランセやミニシアターで見た、地図上でも、どこ?みたいな、行ったこともない場所で撮られた、テロップもナレーションもない、あのドキュメンタリー映画たちが、頭のスミにある。自分の知っている、見ている世界は、ほんの僅かなのだなと、その不可思議さや、広さを、突きつける重さ。暗闇のスクリーンに映った被写体を、ひたすらにじっと見つめる態度の中に、言語化できない感情や価値が、潜んでいるような。
カメラに囲まれた暮らしの中で、カメラが「本当」を映すと無邪気に信じることができないのは、知っているけれど、「本当」と「虚構」の境界を曖昧にするような、破壊力が、子供たちが映っていると、ある気がする。子供たちは、カメラと素直な関係を作り、自由で、恐れ知らずで、生き生きとして、虚実をも超える。子供が大人を見つめる表情、カメラの前での佇まい、生きてきた姿は、さらりと、フレームを超えて、彼らを待ち受ける、将来、未来までをも、想像させ、見る人へグサリと突き刺さってくる。
それは、作り手の、子供たちを撮影する眼差しからも、滲み出ているからだと思う。カメラとの距離を無効化できない、作り手の優しさ、厳しさ、怒り、楽しさ、偽り、透明さ、いろいろなものが、じわりと映っている。これから、少しずつ大人になっていく子供たちを、どう捉えるのか。どの位置にカメラを置くのか、どういう距離感で撮影するのか、どういう表情や言葉を編集して使うのか、大人と子供の関係をどう映しているのか。
どんな映画でも同じだと思うけれど、取捨選択の積み重ねの過程の中に、言葉では説明できない思考の集積が、映し出されている気がする。
そんなことを、考えながら、選んでみました。
1979年生まれ。『嘘つきみーくんと壊れたまーちゃん』(2011)で商業長編映画デビュー。主な監督作品に、映画『5windows』シリーズ(2011-2015)、『PARKS パークス』(2017)、『ジオラマボーイ・パノラマガール』(2020)、ドラマ「セトウツミ」(2017)、「声ガール!」(2018)、「カレーの唄。」(2020)、「あのコの夢をみたんです。」(2020)などがある。最新作は、Amazon Original映画『HOMESTAY』(2022)。

「若く新しい観客にどんなドキュメンタリー映画を観てほしいか」と問われて、まずは自分の映画を紹介したいという誘惑に駆られた(映画を作る人間なら、誰でもそうじゃないの?)。しかしそれではあまりに手前味噌なので、潔くやめた。
次にいわば“教養”として観ておかなくてはならぬ古典を紹介したらどうかと考えた。しかしそういう仕事はすでにさまざまな作り手や専門家によってなされているだろうし、どうしてもドキュメンタリー映画を“勉強”するという感じになってしまう。
もちろん、古典を系統だって観てドキュメンタリー映画について勉強すれば、毎年公開されるドキュメンタリーの新作を観る際にもその面白さはぐんと増す。だが、たとえそういうステップを踏まず、何の予備知識なく観ても、優れたドキュメンタリーは面白いし、エキサイティングである。だからそのことを実感できるような作品を選ぼうと考えた。しかもどうせなら、僕以外に誰も紹介しそうにない作品を紹介した方がよい。
幸か不幸か、僕のドキュメンタリーの鑑賞体験は、日本に住む多くのドキュメンタリー・ファンと比べて、ずいぶんと偏っている。どう偏っているかというと、僕は海外の映画祭で世界各国の新作ドキュメンタリーを観る機会が、はるかに多いだろうということである。
というのも、僕は自分の新作が完成するたびに、映画とともに世界中の映画祭を巡る。映画祭に行けば、自作の上映や質疑に出席するだけでなく、時間が許す限り、そこで上映されているさまざまな新作映画を観ることになる。時には審査員として映画祭に出席するので、そういう場合には作品を観て議論するのが主な目的になる。
そういう過程で、僕は実にさまざまな、世界のドキュメンタリー・シーンの最前線にある、活きのいい作品群に出会う。ところがそれらの大半は、日本では劇場公開はおろか、映画祭でも上映されることがない。そのことが常に僕の不満であり続けている。まあ、日本のドキュメンタリー映画の大半も海外では公開されないので、これは日本の問題というよりは、国境の問題なのではあるが。
だからこのリストでは、若く新しい観客に観てほしいけど、日本ではまったく上映されたことがない作品だけを挙げた。
「じゃあ、観たいと思っても、観れないじゃないか」とお怒りになるなかれ。前回の「現代アートハウス入門 Vol.2」では、企画運営の東風に日本で未公開の『セールスマン』(1969年、アメリカ、監督:アルバート・メイズルス、デヴィッド・メイズルス、シャーロット・ズワーリン)を提案したところ、協力会社のノームと一緒にわざわざ権利を買い付けて上映が実現した。
もちろん今度もそうなるとは限らない。しかし「欲しいものリスト」が存在しなければ、欲しいものは永久に手に入らないどころか、欲しいものが何なのかすらわからないのだ。
このリストに挙げた作品が、いつか日本でも観られる日が来ますように(東風さん、お願いします!)。どれも凄いですよ。観られないなんて、本当にもったいない。
1970年生まれ。自ら「観察映画」と呼ぶ方法論を提唱、実践。その第1弾として2007年に発表した『選挙』は米国でピーボディ賞受賞、ベルリン国際映画祭正式招待。続く『精神』『演劇1・2』『牡蠣工場』『港町』など、いずれも名だたる国際映画祭で上映される。最新作『精神0』はベルリン国際映画祭エキュメニカル審査員賞、ナント三大陸映画祭金の気球賞(グランプリ)を受賞。

観察映画の想田和弘さんが、「見たことのないものを見たいという欲望が映画を発展させた」と、『極北のナヌーク』をドキュメンタリー映画のはじまりとして紹介しているBRUTUSの記事を読んだ。要約すると、「批評家が“この作品にはドキュメンタリーバリュー(記録的な価値)がある”と評したことがきっかけで、ドキュメンタリーというジャンルができた。面白いのは、あちこちに演出が入っていること。主人公の本名は実はナヌークではないし、ナヌークの妻として登場する女性は監督の現地妻。イグルーの中も普通に撮影したら光量が足りない。そこで壁が半分だけのイグルーを造って撮った。ドキュメンタリーの誕生には、それほど虚構の要素が入り込んでいる。でもそれがドキュメンタリーの起源であるというねじれが面白い。しかしいくら虚構の要素が強いとはいえ、この映画には当時のイヌイットの顔や生活が確かに映っている。ドキュメンタリーバリューがあるんです。実は1895年に映画を発明したリュミエール兄弟が作った数多くの短編映画も、今から見ればドキュメンタリーです。映画はその始まりから、“見たことのないものを見たい”という文化人類学的な欲望によって駆動されたのです」
この事は、私たち空族が映画を考える上で非常に重要な示唆に富んでいるが、先日もドキュメンタリー映画研究者であるマーク・ノーネス氏との交流の中からも知り得た事柄があった。「プロキノ」の存在だ。これは「日本プロレタリア映画同盟」の略で、1929年発足、1934年弾圧により解体となったが、そんなに早い時期に、日本国内においてフィルムでドキュメンタリーが作られ政治運動と結びついていた、という事実に驚いたのだった。そもそも、リュミエール兄弟の発明から、フィルム(映画)が日本に持ち込まれた早さに改めて驚愕するが、その後の日本映画史の充実ぶりには、それらの事が大きな要因になっていたのだろうと得心したのだった。
「見たことのないものを見たい」は「みんなが見たことのないものを見せたい」という欲望と対になり抵抗運動と結びついていったのだろう。そして、いつだってそれらドキュメンタリー映画の殆どは、例えば、歴史モノ超大作などとは真逆に、圧倒的少数の撮影クルーによって成されてきたのだ。
※プロキノ作品集は未見であり、『極北のナヌーク』はここで触れているため選びませんでした。
1972年生まれ。空族。2011年の『サウダーヂ』でナント三大陸映画祭グランプリ、ロカルノ国際映画祭独立批評家連盟特別賞、毎日映画コンクール優秀作品賞&監督賞などを受賞。2016年の『バンコクナイツ』では第69回ロカルノ国際映画祭インターナショナルコンペティション部門で若手審査員賞を受賞。最新作は『典座-TENZO-』(2019)。

ドキュメンタリーの多様さ、自由さ、またドキュメンタリーにおける真実と嘘とは何か考えさせられるのと同時に、人間そのもののわからなさが魅力の作品を選んだ。
ビクトル・エリセ監督の『マルメロの陽光』(1992年)は、シンプルでありながら生々しさとは別の、カメラがそこに存在しないかのような臨場感を覚える。朽ちていく庭のマルメロの変化に合わせて写実し続け、一向に完成しない「過程」を作品としたアントニオ・ロペス・ガルシアの静謐な眼差しが、この映画の視線にも貫かれている。
三里塚シリーズで名高い小川紳介監督の『圧殺の森 高崎経済大学闘争の記録』(1967年)は、あくまで弱い立場の学生たち側に立ちながらも、集団が結束するある種の気味の悪さや、決裂していく非情さが描かれている。権力に立ち向かうため繰り返される白熱した議論は、次第に疲弊し、不毛な堂々巡りへと変容し、やがて摩耗していく。自分とまったく違う他者にカメラを向けるというのは容易な作業ではない。目の前の人を信じるだけでなく、時に疑うことも必要である。
作り手と被写体それぞれの恐れ、疑い、信頼する「距離感」は必ず画に映るものだ。その距離感を意識しながら見ると、ドキュメンタリーは数倍面白くなる。『FAKE』(2016年)は、世間を騒がせた音楽家の佐村河内守氏と監督の森達也氏が、疑い、信じ、また疑う、その果てない応酬が切り取られた作品と言える。佐村河内氏がカメラの前で演じる彼自身の姿から、白黒付け難い真偽の「間(あわい)」が見えてくる。
真実とはなんと脆く、不確かなものか。人によって見える真実が違う、ということを教えてくれる作品のもう一つに、俳優サラ・ポーリーが監督した『物語る私たち』(2012年)がある。亡くなった奔放な母親と隠された実の父親を巡って、家族、友人等、複数の人間から異なる証言が語られていく、ユーモアに溢れた家族の物語だ。インタビューをベースに、家族の8ミリビデオと再現ビデオと思しきフィルムが入り混じり、さらにスタジオでナレーションを録る姿まで記録され……と複数のレイヤーが重なった複雑な構成で、多彩な記憶の位相が描かれている。
ジャン・ルーシュ監督の『人間ピラミッド』(1961年)は、与えられた設定で本人が本人役を演じる、半ドキュメンタリーの実験的劇映画である。人種間の差別と交流を描いた青春群像劇で、黒人と白人の学生たちに監督自ら「君たちの何人かにレイシストを演じてもらう」と説明するシーンから始まる。現在で言うところのメタフィクションあるいはリアリティーショーであるが、この映画を観るとドキュメンタリーとフィクションの違いと定義付けが、実に曖昧なものであることがわかるだろう。人間はそもそも演じる生き物だ。出演依頼に応え、カメラの前に立つこと自体、それはもう作られた世界とも言える。虚と実の間で何を感じるか、まずはじっくりと見つめてほしい。
1987年生まれ。2011年より分福に所属。是枝裕和監督や西川美和監督のもとで監督助手を務める。2019年に柳楽優弥主演の『夜明け』でオリジナル脚本・監督デビュー。同年12月にドキュメンタリー映画『つつんで、ひらいて』を発表。21年に放送された連続ドラマ「それでも愛を誓いますか?」で監督を務める。

若い観客に。と問われると途端に何を根拠にオススメすればよいのか分からなくなる。
若い観客だから、若々しい作品? 希望に満ちた作品? 勉強になるような作品?
別にどれも悪い訳ではないけど、そういった属性を最優先に選んでしまうと何かもっと映画の豊かな何かを逃してしまう気がして悩んでしまう。大体、自分が若かった頃に特別そういった作品を好んで見ていたなんてことは絶対になかった。それらはどこか年を食ってから、作り出されたありもしない「若者像」なのではないだろうか。
ということで、結局、「自分が今よりずっと若かった時に面白いと思ったものは今の若者が見ても面白いに違いないと盲信し、それらをただ勧める」ことにしました。想定年齢としては自分が10代の頃から大学生ぐらいの時までにみた「ドキュメンタリー映画」で心を強く揺さぶった作品、大好きだった作品を選びました。問題は相応に年を取ってしまったのとぼんやり生きてきた人間なので、古い記憶が混濁してしまっていること。これらは何かのはずみで海馬の底からパッと飛び出てきた作品たちで、多分、明日選べばまた違うならびになること間違いありません。
上記5本を見て、中には『メキシコ万歳』や『快適な生活』のような厳密に言ってドキュメンタリーなのかどうかも曖昧な作品もある。しかし、そもそもドキュメンタリーとフィクションを形式的に分類することはできても、そこに境界線を「厳密」に引くことは無理だろう。約130年前、リュミエールがラ・シオタ駅のホームに家族や友人を集めてカメラの前に立たせたそのときから、フィクションとドキュメンタリーが不可分に結びついた混合体として映画は誕生したのだ。
一方で、フィクションとドキュメンタリーの境目は曖昧だからこそ、そこにカメラなんてありませんよ、と俳優たちが素知らぬ顔で演じてみせるフィクション映画だけではなく、カメラの影響下にある人間たちを目の当たりにできるドキュメンタリー映画もまた面白い。だからこそ、映画とはカメラそのものであることを楽しげに宣言した『これがロシヤだ/カメラを持った男』(ジガ・ヴェルトフ)を若者はまず見てもよいのかもしれない。あ、一本増えてしまった。
1980年生まれ。2013年『ほとりの朔子』がナント三大陸映画祭グランプリ金の気球賞と若い審査員賞をW受賞。2016年『淵に立つ』がカンヌ国際映画祭「ある視点」部門審査員賞を受賞。2018年、フランス芸術文化勲章「シュバリエ」受勲。そのほか主な劇場公開作に『よこがお』(19)『本気のしるし〈劇場版〉』(20)など。最新作は『LOVE LIFE』(22)。

死ぬまでに現実世界で出会えなかったこと、目の当たりに出来なかったこと、触れられなかったモノはどれくらいあるのでしょうか。私にとって良質な映画とは欠落した過去の記憶を埋めてくれる存在であり、未来を生きる道標でもあります。
今回はその中でも特に、自分の人生で必要だったと思えるドキュメンタリー映画を5作品を挙げました。
『マルメロの陽光』では、画家・ロペスさんの仕事を通して自然の深淵さと芸術を極める果てなき道を歩む覚悟を知り、
『ヴァンダの部屋』では、遠く離れたリスボンの土地で描かれる人と町の生と喪失の断片から今自分の立つ場所を慈しみ、
『三姉妹〜雲南の子』では、山岳地帯に暮らす幼い少女たちの日常の背景にある理不尽な社会に対して何ができるのかを問われ、
『ミッドナイト・トラベラー』では、アフガニスタンから逃れる家族の一心不乱に記録した旅路に物語ることの力強さを再確認し、
『ドキュメンタリー映画100万回生きたねこ』では、世代や国境を越えて物語の魂が巡っていく様が可視化され、芸術を人が紡いでいく奇跡を目撃しました。
これらに共通しているのは映画制作に取組む姿勢を教えてくれた作品群です。現実世界にある事象から切り取られたドキュメンタリーの手法は、物語と自分の暮らしの距離の近さが魅力だと感じています。
“人生で必要だったと映画”と書くと大袈裟に聞こえるかもしれません。しかし、刹那的な感覚で面白い面白くないという基準での鑑賞体験以上に、映画は人生に寄り添ってくれるような、「自分の記憶」と錯覚するような瞬間があります。他者の眼差しを通したモノであるにも関わらず不思議なことです。
あなたにとって映画とはなんですか?スクリーンに映るものは有限ですが、その解釈の仕方には無限の広がりがあります。本企画が大切に思える映画と出会えたり、思い返すきっかけとなればと願います。
1988年生まれ。2017年の長編初監督作『僕の帰る場所』が東京国際映画祭「アジアの未来」部門2冠や海外映画祭にて受賞を重ねる。続く2020年の『海辺の彼女たち』はサンセバスチャン国際映画祭の新人監督部門に選出され、新藤兼人賞金賞、大島渚賞、日本映画批評家大賞新人監督賞などを受賞。

正直なところドキュメンタリーとは何か自分はあまりよく分かっていません。すべてがドキュメンタリーであり、フィクションであると思っているからです。今回その様な仕切りを考える事がなんだかバカらしく思えるような映画を選んでみました。
今やそこに誰かがいた事を記録する事自体案外たやすく、誰もが撮影・記録できる世の中で、それを記憶とどう折り合いをつけていくのか、それは温度なのか体感なのか、忘却の波が日々をかき消し記録がうずまき、気がつけば自分もどんどん記憶が記録に書き換えられていく実感の中にいます。
今自分自身高知県に住んでいるのですが、移住を機に読み始めた宮本常一、柳田國男など民俗学者のなにやら登場人物が被害者、加害者…というような記号的な立ち位置で、一方的に語られるのではなく、皆地に足をつき観察とも違うまるで自分の身の回りをほっつき歩いてそうな、普通の人間として映し出される宮本常一「忘れられた日本人」の土佐源氏に書かれた馬喰と聞き手の様な語りの距離間にここ数年意識をよせています。
民俗学が人や土地を後世に語り伝えてきたように、その土地に通い続ける中で見えてくるものが、その土地に根ざしているものとの距離の中で変わることがあるのでしょうか?
今回選んだ映画は、なにやら撮影の過程で気配あるいは痕跡の方に惹かれていって、土地そのものが顔の様に映っている、何より一瞬の衝撃からのみ見えているものを疑い、堂々と嘘をつき、映画的驚きと共に痕跡から現実と地続きの軌跡をすくい上げていると思っています。
『路地へ 中上健次の残したフィルム』『SELF AND OTHERS』は、主人公がもはや現実にいない姿形もない。輪郭をなぞる様に、そこにいた痕跡をひたすらカメラは運動の中で朧げに浮き上がらせていく。『ワン・プラス・ワン』『書かれた顔』はフィクションとドキュメンタリーの行き来の中で、その場に今いる人と土地に語り継がれている記憶を縫い合わせる。『ヴァンダの部屋』はその土地に撮影隊が根付く事で土地ごと撮影という行為の中に音と共にすくいとる事ができた様に、すべての映画がそれぞれ独自の距離を計りながら運動の中に弔いとも違う、死から得られる生命力をどこか映画が身につけて映画は終わりをつげる。そんな映画を劇場という場所で、他人と誰のものでもない夢を暗闇で見つめる体験を共有してほしいです。
映画は観れば観るだけ自由になっていきます。全ての動きがアクションでありダンス、全ての音が音楽のような感覚で見てみるのも面白いかもしれません。
最後に自分自身の話になってしまいますが、学生時代青山真治監督の『路地へ』を見て、この技術部は小川紳介監督の技術部なのか…ほぉほぉ、撮影田村正毅、音響菊池信之、菊池さん田村さんの他の作品を見てみようと、枝葉の様に映画を見てくのもおすすめです。
1992年生まれ。2016年、監督・脚本・音楽を務めた長編映画デビュー作『はるねこ』がロッテルダム国際映画祭コンペティション部門に選出、イタリア、ニューヨークなど多数の映画祭に招待された。映画制作だけでなくMV制作や音楽活動も行い、2019年には四人組バンド「Bialystocks」を結成。2022年11月監督最新作『はだかのゆめ』公開予定。

いわゆる主人公がおらず、物語(ストーリー)をけん引する言語やテキストがない映画を選んだ。どの映画もインタビューもなければ、ナレーションもない。物語を紡ぐようなセリフもないが、独特な映画体験を得たことがある。これらはナラティブな映画ではないが、見終わった後、独自の物語を頭の中で作れるような気がしたからだ。これらの映画について私よりも詳しい人がこれらの映画のファンの中にたくさん居るということを知っている。劇場で一緒に見たことで得られる映画体験を共有したい。
2012年の1月に、5日間くらいの期間でインドのコルカタでドックエッヂコルカタというワークショップに参加した。サタジットレイ映画学校で寝泊まりし、欧米やアジアの番組決定権者、制作者向けにドキュメンタリーのピッチ(企画プレゼン)を行うのが目的だ。ピッチのお作法を習う、教育プログラム的なワークショップだ。その時に古典とともに2012年ごろの最新の映画を見る機会があり、ここに挙げている作品などを見た。
そこには20人ほどの若手のドキュメンタリスト(学生)がいた。インドをはじめマレーシアやネパールなどアジア諸国からきていた。4班に分かれ、そのチームごとにピッチの練習が行われる。当然、その時にチーム内で友人ができ、今も数名だが交流は続いている。毎晩、そういう友人らとドキュメンタリーについて語り、講師としてきている巨匠たちの映画を鑑賞し、その監督に敬意を払いつつ、QAで質問攻めにしていた。その時見た映画の中には映像を言語化したメッセージがなく、これらの映画にある可能性を感じた。
ここに挙げているドキュメンタリーを見るうちに、映像そのものが語るということを思い知った。映画の制作過程を監督からそのまま聞くと、すごくその内容が腑に落ちた。ジャーナリズム的な手法のドキュメンタリーこそが王道だろうと思い込んでいた時期だったので、古いものから新しい映画の可能性を知れたことに目からうろこだった。
1979年生まれ。2009年の『花と兵隊』で田原総一朗ノンフィクション賞奨励賞、山路ふみ子映画賞福祉賞を受賞。2013年の『祭の馬』は東京フィルメックス・コンペティション部門、アムステルダム国際ドキュメンタリー映画祭など多くの国際映画祭に招待され、ドバイ国際映画祭ドキュメンタリー・コンペティション部門最優秀作品賞を受賞。最新作は『オキナワ サントス』(2020)。

ある人間が自分自身を演じている姿を記録したものか、自分以外の誰かを演じている姿を記録したものか。ある種のドキュメンタリー映画と劇映画を区別するとしたら、演じる役が「自分か他人か」という点にあり、キャメラが存在する以上は「演じる姿の記録」である点では共通しているように思う。こう書くとまるで漫才とコントの違いのようだけれど。
ここで、では「自分」や「他人」とは何か、という問題も浮上しそうだが、深くは突っ込まずにおく。あくまで、「自分」は単一の存在でなく複数の面(面?)から成り立っているものだと、ぼくは理屈抜きで直感している。
人は一体なんのために古代から「演じる」ことを続けてきたんだろう? 答えは知らないが、考えるのは楽しい。ともかく、「演じる」姿というのは、本当に、あまりにも多様で、謎めいていて、見ていて全く飽きない。
それにしても、キャメラを通して「演じる」姿をみても、その人が正確には何を考え思っているかなんて全然わからない。だから、カット割によって心理を捏造する技術もあるが(例えば「テラスハウス」のような編集)、それをなるべく排して別のやり方を目論むならば、心理でなく体の動き(もっといえば体に起きる事件)つまりアクションを徹底的に捉えることになる、らしい。その前には、人はそう簡単には動かないから、「演出」も生まれているのだが。ところで、「捉える」も不思議な言葉だ。「ただ撮ってる」感とでもいえばいいか。妙な生々しさになぜかどきどきする。とはいえ、「ただ撮ってる」なんて果たして可能なのか?
それから、何十年も前に作られた映画をみると、たとえファンタジー映画だとしても「当時の人たちはこんな風に動いたり話したりしていたのか」という発見に夢中になって物語展開を忘れることがある。今年話題のあの新作たちもいつかの未来には、この時代の記録映像として愉しまれたりするのだろうか?
と、上記のようなことを考えながら、通常はドキュメンタリーと分類されない映画、またなるべく近年の映画から選んでみることにしました。
『アウトレイジ 最終章』は「ただ撮ってる」ようにしか思えない。ある人物からある人物へとキャメラがふらりとパンした瞬間、ギョッとした。役者の演技が物語にただ奉仕することに抵抗しているのだろうか。獰猛な動物たちがただ記録されている、という感じ。比べると過去作はキマりすぎている気すらしてくる(そのキメっぷりがすごくてどれも大好きだが)。ところでもしフレデリック・ワイズマンがヤクザ組織を題材に撮ったらどうなるだろう?
『百年恋歌』は、長年にわたる舒淇&侯孝賢の仕事の経過報告記録としてみるとどうなるか。ジーナ・ローランズ&ジョン・カサヴェテスの仕事でも、デンゼル・ワシントン&トニー・スコットの仕事などでもいい。演技と演出の長期的な記録。
『6才のボクが、大人になるまで。』の驚きは上記にも通じる。長期間にわたる、ある人物たちや社会の変化の記録。『ビフォア』シリーズあるいは『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』にも、ただの同窓会映画以上の感動があった。もちろん小川紳介はじめ『空に聞く』『風の波紋』『春を告げる町』など長期間にわたって撮影された映画にも……とは書くまでもないか。
『ハドソン川の奇跡』は、役者と当事者たちによる事件の再現という不気味な映画で、レコーダー映像を「ただ撮ってる」あたりの異様なサスペンスが凄い。イーストウッドは続いて当事者が自分自身を演じるという謎の企画『15時17分、パリ行き』まで撮っている。一体彼は何を企んでいたのか? そういえば『1000年刻みの日時計 牧野村物語』やオリヴェイラの映画にも似た企みがあったような……。
『エリ・エリ・レマ・サバクタニ』は、ここに『路地へ』や『AA』を置くべきかもしれないが、二人組のミュージシャン「ステッピン・フェチット」の貴重な記録でもある。あの二人が、掃除機や貝殻や楽器を手にし、無言で音を探りながら時に微笑む、あの豊かで美しい時間は、見ていて最高に楽しいし、本当にたまらないものがある。
1984年生まれ。2012年、『Playback』がロカルノ国際映画祭コンペティション部門に選出。2018年の『きみの鳥はうたえる』は毎日新聞映画コンクール、キネマ旬報ベスト・テンなどで主要賞を多数受賞。2020年にはNetflixオリジナルドラマ「呪怨:呪いの家」を監督。最新作『ケイコ 目を澄ませて』はベルリン国際映画祭エンカウンターズ部門に選出された。

二十歳前後のときに出会い、立っている地平を揺るがせてくれた5本。
スペインの画家、アントニオ・ロペスの一番の目的は、作品を完成させることではない。描きたい構図のために、刻一刻と変化してしまう光、熟すにつれて垂れ下がるマルメロを、写真に撮っておさめようとはしない。抗わない。もっとも大切なのは、愛するマルメロの木の側で描くということ。「諦めも肝心なんだよ」と微笑む姿に、地上の生の豊かさを知った。「若いうちこそとにかく作って作りまくれ!」という言葉をかけられて、息苦しさを感じていた頃に観て、スッとした。どうか劇場で観たい。
わたしはしばしば、自分という存在を一切忘れたいがために映画を観る。しかしこの映画はそれからほど遠いところにあり、訳も分からず泣いた。自分に引き寄せすぎてしまったのだと思う。そのように映画を観ることを避けていたのに、簡単に共感し、泣いた自分が、とにかく不快だった。恥ずかしいけれど、わたしには小野さやか監督のように、死ぬ気で何かと向き合ったことがないという悔しさから出た涙だったかもしれない。比べることではないけれど。デッドボールくらって、逃げるようにして帰った。
こんなに強くて(ムキムキで)優しい人を見たことがない。シジミをとって稼いだその日暮らしのわずかなお金のほとんどを、多摩川に捨てられたたくさんの猫たちのご飯に使い(カリカリだけじゃなくてウェットフードも!)、「こいつらにだって生きる権利はある」と語る。そうだよ、みんなが一緒に生きている。魅力溢れる人間を中心に捉えるドキュメンタリーは多くあるが、今作はそれだけでなく、このヘルジャパンの搾取構造をもうつし出す。悪しき政治家の皆さん、見たいもの以外を無視した暮らしは楽しいですか?
ベッドから一切動かず、大声で娘を呼びつける老いた母、ビッグ・イディと、おしゃれに着飾って歌って踊る50歳を過ぎた娘、リトル・イディ。この二人、ジョン・F・ケネディの親戚であり、かつては華々しい生活を送っていたようだが、今や社会と断絶し、アライグマの住処になるほどのおんぼろ屋敷でお互いをギャンギャン罵り合っている。この映画の被写体になることが、外部と接続できる悦びだと言わんばかりの躁状態ぶりだ。ふたりともパワフルでエキセントリックなので、なんだか愉快に思える暮らしぶりだが、わたしには決してそう思えなかった。もはやどこにも行けないから過去にすがる娘と、彼女を縛り付ける母の共依存関係が、とても悲しい。
ハリウッドがどのように同性愛を捉えて描いてきたのかを、100本を超える映画資料と、関係者のインタビュー形式でたどった95年製作のドキュメンタリー。今では、セクシャルマイノリティの普遍的な日常を描いた映画が多く見られるようになったが、かつては、登場しては死んでしまう犠牲者か、倒錯した加害者としてばかり描かれていた。映画の影響力が大きかった時代に、作り手はどこまで自覚的だったのだろうか。Netflixドキュメンタリーの「トランスジェンダーとハリウッド:過去、現在、そして」と併せて、全ての人に観てほしい。
他に、森達也監督『A2』、佐藤真監督『SELF AND OTHERS』、原一男監督『全身小説家』も悩みましたが、だれか他の方が入れてくださることを願って、割愛しました。
1997年生まれ。2017年の初監督作品『あみこ』がPFFアワードで観客賞を受賞、翌年のベルリン国際映画祭に史上最年少で招待され、10カ国以上で上映される。2019年、オムニバス映画『21世紀の女の子』の一編「回転てん子とどりーむ母ちゃん」を監督。2020年、文化庁委託事業「ndjc:若手映画作家育成プロジェクト」で監督作『魚座どうし』を発表。

一度観たきり随分時間が経った作品もあるが、もう一度スクリーンで観たい5作品を挙げた。
アイヌ民族の儀式である「イヨマンテ」を準備段階(神に返す熊を育てるところ)から追っていく。映画は、後世に残すためにと1977年に二風谷で行われた儀式を記録した作品だが、祭祀道具を作る人々の細やかな手つきや、熊の肉体を解体し丹念に変容させ神に返すまで、画面に映るすべての営みの美しさにただただ圧倒された。その衝撃が、自分がアイヌ文化に関心を持つきっかけとなった。
戦後の子供たちの記録としてもかなり重要だと思う。そしていつ観ても70年前の子供たちが画面の中で鮮烈に輝き続けている奇跡。子供たちの自然な佇まい(を捉えたこと)が評価されているように思うが、やや強引とも思える物語化されたナレーションに、羽仁監督特有のフィクション性を強く感じる。
1926年のサイレントオリジナル版に音楽や会話をつけるという大胆で実験的な試みに感服した。その時点で大いに演出が付け加えられたと言えるが、映像だけを見ても撮影時点で多分に演出がなされているように思った。元祖ドキュメンタリーと言われている本作だが、ドキュメンタリーとフィクションの境界とはなんぞやと考えさせられる。
撮影当時ヴァルダ監督自身が幼子の子育てで活動範囲を限定していたことが、自身の生活圏内であったダゲール街で映画を作ることに結びついたようだが、自分の生活している場所でそこに住む人々にカメラを向けるのは中々勇気の要ることではないか。たくさんの商売人たちが映る。彼ら一人一人が持つ「個」を見つけ、個と個が街の中でどのように繋がっているのかをゆっくりとあぶり出し、「夢」の話へと導いていくヴァルダ監督の独創的な語り口が面白い。
この一見奇妙な母子に眼差しを向けたとき、「セルフ・ネグレクト」「毒親」「共依存」等の現代用語が頭を駆け巡って、映画とどう対峙すればいいのか戸惑うのだが、そんな価値基準は徐々に無効化されてゆき、彼女たちの圧倒的な面白さと、その存在の尊さにいつの間にか魅了されている。彼女たちの日々の営みには「人って、こんな風に立ったり歩いたり話したり歌ったりするのか」という再発見がいくつもあり、普段フィクション映画で俳優に演出する立場である自分は大いに刺激を受けた。
1978年生まれ。自主制作映画『ジャーマン+雨』(2006)が全国で劇場公開される。09年の『ウルトラミラクルラブストーリー』で商業映画デビュー、TAMA CINEMA FORUM最優秀作品賞などを受賞。代表作に『りんごのうかの少女』(13)、『俳優 亀岡拓次』(16)ほか、最新作は『いとみち』(22)。

ルイジアナの広大な湿地帯で両親と暮らす少年アレクサンダー。自然と野生動物に囲まれた生活は、父親が油田掘削の許可書にサインしたことで大きく変わっていく…。『極北のナヌーク』『モアナ』などで知られるロバート・フラハティ監督による物語映画として世界映画史にその名を刻む本作だが、もとは石油会社のPR映画だった。野生のワニやアライグマなど“ドキュメンタリーバリュー”もたっぷり。

舞台はコートジボワールのアビジャン。地元の高校生の人種差別問題に気づいた映像人類学者のジャン・ルーシュは、この問題を主題に16ミリ映画を撮ることを思いつく。生徒たちは黒人と白人の間の新たな関係を通して生まれる友情関係、愛情関係についての「フィクション」に自分自身の役を演じながら参加するのだが…。エリック・ロメールやジャン=リュック・ゴダールも絶賛したルーシュの代表作の1本。

三里塚から山形・牧野へ移住し、田畑を耕しながら映画制作を続けた小川プロの13年の集大成。稲の生殖の営みや水田のなかの考古物の発掘など科学的アプローチに加え、村に何世代にもわたって語り継がれる口承の物語を、土方巽、宮下順子、田村高廣ら職業俳優とともに、牧野村の人びとが“ドラマ”として演じてみせる。1000年という歴史と牧野の風土が編みこまれた、映画史上類を見ない傑作。
 © Straub-Huillet / BELVA Film
© Straub-Huillet / BELVA Film詩人ジョアシャン・ガスケによる評伝「セザンヌ」に記された空想的な対話の朗読に重ねて、セザンヌゆかりの土地やセザンヌの絵画が映し出される。実物の絵画を直接撮影している点では記録映画であり、ガスケによって虚構化されたセザンヌという人物の言葉を劇的に再虚構化している点では劇映画にも近い。ポール・セザンヌの過激な絵画観に、過激な映画作家ストローブ=ユイレが肉迫する。

歌舞伎界で当代一の人気を誇る女形、坂東玉三郎。「鷺娘」「積恋雪関扉」といった舞台や、芸者に扮した彼を2人の男が奪い合う劇「黄昏芸者情話」が挿入され、玉三郎の秘密へと観る者を誘う。俳優の杉村春子や日本舞踊の武原はんの談話、現代舞踏家の大野一雄の舞いなども。現実と虚構さえもすり抜けていくシュミットのスイス・日本合作となった本作では、青山真治が助監督を務めた。
 © 牛腸茂雄
© 牛腸茂雄1983年に36歳で夭逝した写真家、牛腸茂雄。郷里の新潟、ときに死の不安に苛まれながら写真家生活を営んだ東京のアパートなどゆかりの地を巡り、彼が遺した痕跡を辿る。被写体の眼差しを焼き付けたようなポートレート、姉に宛てた手紙、そして、見つけ出されたカセットテープ。しだいに彼の不在そのものがかたどられていく。撮影に田村正毅、録音に菊池信之が参加。手紙の朗読を西島秀俊が務めた。
 © 2012 National Film Board of Canada
© 2012 National Film Board of Canada太陽みたいに明るく無邪気だった母ダイアン。彼女が亡くなったとき、末っ子のサラはまだ11歳だった。「サラだけがパパに似てない」、ポーリー家おきまりのジョークにサラは少し不安になる。母の人生の真実を探り出そうとカメラを向けると、みんなの口からあふれ出したのは彼女の知られざる恋について——。俳優で映画監督のサラ・ポーリーが、自身の出生の秘密をウィットとユーモアをこめて描く。
| 地域 | 劇場名 | 電話番号 | 開催日程 |
| 東京 | ユーロスペース | 03-3461-0211 | 10月22日(土)〜11月11日(金) |
備考:上映スケジュールはこちら▼10/22(土)18:50『書かれた顔』上映後 トーク:甫木元空さん(映画監督/Bialystocks)× 須藤健太郎さん(映画批評家) ▼10/26(水)18:50『SELF AND OTHERS』上映後 トーク:草野なつかさん(映画作家) × 小森はるかさん(映像作家) |
|||
| 愛知 | 名古屋シネマテーク | 052-733-3959 | 11月12日(土)~11月25日(金) |
備考:上映スケジュールはこちら▼11/12(土)19:20『SELF AND OTHERS』上映後 レクチャー:想田和弘さん(映画作家) |
|||
| 大阪 | シネ・ヌーヴォ | 06-6582-1416 | 11月3日(木)~11月15日(火) |
備考:上映スケジュールはこちら▼11/4(金)18:45『書かれた顔』上映後 トーク:小田香さん(映画作家)× 菊池信之さん(映画音響技師) |
|||
| 京都 | 京都シネマ | 075-353-4723 | 11月11日(金)~11月24日(木) |
備考:上映スケジュールはこちら▼11/13(日)14:00『SELF AND OTHERS』上映後 レクチャー:想田和弘さん(映画作家) |
|||
| 鳥取 | ジグシアター | 12月3日(土)〜12月9日(金) | |
備考:上映スケジュールはこちら▼12/3(土)10:00『人間ピラミッド』上映後 佐々木友輔さん(映画監督)による〈ドキュメンタリー映画史ガイド〉 ▼12/4(日)15:30『セザンヌ』上映後 深田晃司さん(映画監督)による〈作品レクチャー〉 ▼12/7(水)17:00『1000年刻みの日時計 牧野村物語』上映後 モリテツヤさん(汽水空港 店主)による〈トーク〉 |
|||